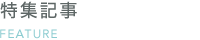手放せない未読の本はどうしたらいい?|ミニマリストおふみの相談室
2024.01.26
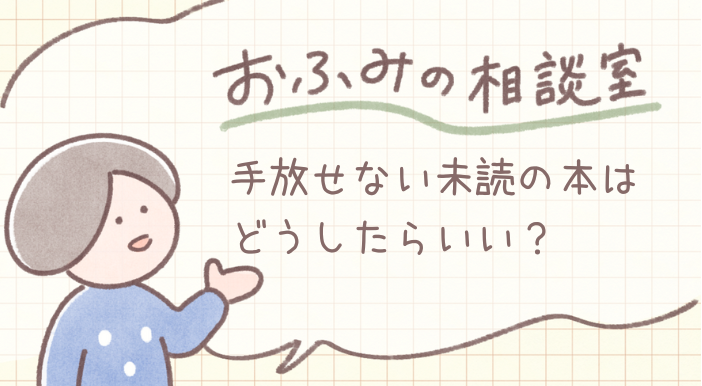
壊れていたり不要なものは手放せた方でも、手放すハードルが高いのが“まだ使えるもの”。特に、一度も使っていないようなものは、手放すハードルがグンと上がると感じるのではないでしょうか。今回のお悩みは「未読の本を捨てられない」というお悩みです。
道具であれば使っている、使っていないという判断もできますが、未読の本はどう判断したらよいのでしょうか。同じ悩みに直面しているという、ミニマリストのおふみさんに手放すか否かの判断方法と積読(つんどく)対策をご紹介いただいています。
モノを手放していく上で心を悩ませるのが、「まだ使えるもの」ではないでしょうか。今回はこんなご質問をいただきました。
—-
未読の本が捨てられないです
いつか読むかもしれないと思ってしまいます。
—-
私も積読(つんどく=未読で本を積んでいる状態)していてずっと直面している悩みですし、多くの方が共感されるのではないでしょうか。
未読状態の本は「もう読みたくない」のか「読みたいけれど読むことができていないのか」によっても対処が変わります。まずは、それを見極めていきましょう。
自分の中の情熱を測ってみる
基本的にはわざわざお金を出して買ったものなので、過去の自分にとって興味を惹かれたものだったはずですね。
あるいはプレゼントされたパターンもあるかもしれません。
いずれにせよ、読書は自分の目で読んで手でページを捲るという能動的なものです。それゆえにある程度情熱がないと読み進められないものですよね。本の虫だって全く興味のない本は読めないのでは。
そこで自分の中の情熱の度合いを測ってみましょう。
その本を目の前に置いてみてください。
これが手元から消えたとしたら、もう一度買いたいと思いますか?
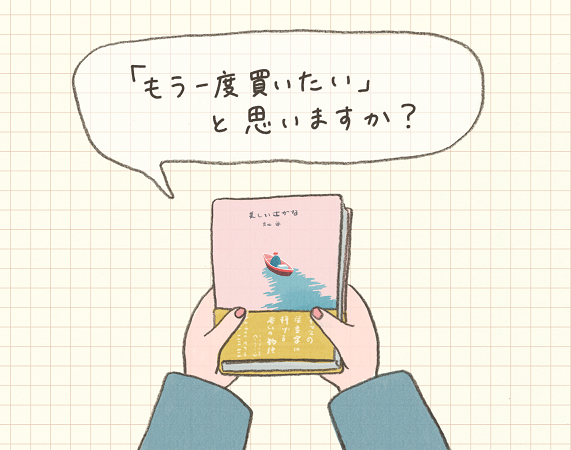
「買い直さない」と思うなら、自分の中での情熱は鎮火しているのかも。
例えば、始めたけれど手が止まってしまった外国語勉強のテキスト、ハンドクラフトの材料や道具など、趣味のものが近しいものだと思うのですが、自分の中で熱量が下がることはあります…人間なので。熱量が下がってしまったのであれば、それを認めて手放すことに許可を出してあげてもいいのでは。
忙しい現代社会、貴重な可処分時間を使ってやりたいことが他にあるなら、それを優先して良いのです。
私の場合は、一時期木工や革クラフトにハマっていて、いろんな材料や端材を集めていました。しかし、いつしか情熱が落ち着いて、何年も放置してしまっていました。
いつか使うかもしれないからと残していましたが、時間ができても結局やらずじまいでした。それなら今もクラフトを趣味にしていて精力的に製作している友人に譲った方が有効活用してもらえて良いと考えて声をかけました。
無事に喜んで引き取ってもらえました。廊下で場所を取っていた大量の木材や革がなくなったことで、物理的にも心理的にもスッキリしました。思えば材料の前を通りがかる度に、ものが発する「もうやらないの?」というメッセージを受け取っていました。そのストレスがなくなり、大きな開放感を覚えたのです。
ぜひ一度、情熱が鎮火していないか自分に問いかけてみてください。
また、本は大抵の場合、再度手に入れられる機会が多いものだと思います。絶版でなければ買い直せますし、絶版になっていてもフリマアプリ等で購入できた経験もあります。またその本が図書館にはあったりもする。商業出版なら国会図書館に収蔵されている可能性も高いです。
後日、本気で読みたくなったら手に入れられるだろう、と思えば手放すハードルが下がりませんか?
読書がしやすくなる環境を作ってみる
先ほどの「もう一度買いたいと思いますか?」という質問で、改めて買い直したいと思ったなら、その本を読みたくなる・読みやすくなる環境を作ってみましょう。
私は寝室の枕元に小さな収納を置いていて、その中に寝る前に読もうと思って買った紙の本を積み上げており、なかなか手がつけられておらず文字通り積読状態です。
しかし、電子書籍だと割とサクサク読めるのです。この理由を分析してみると、自宅で紙の本を読む場面だと、枕元にスマホがありSNSが気になったりして読書の手が止まりがちでした。
反対に電子書籍は、電車で立っている時やバス待ち、診察待ちなど、スマホで読書する以外にあまり選択肢がない時に読んでいます。他に娯楽がない状況なので、意識が逸れて読書が中断することがあまりないのです。
満員電車でSNSをするとなんとなく周囲の目線が気になるし(私だけ?アイコンが見えてしまうのも、タイムラインに流れてくるものが見られる状況なのも気がかりで、安心して見られないのです。)、動画を見るとギガの消費が気になるしで、吊り革を掴んで手が塞がっているので片手でできる娯楽って読書くらいしかないのです。
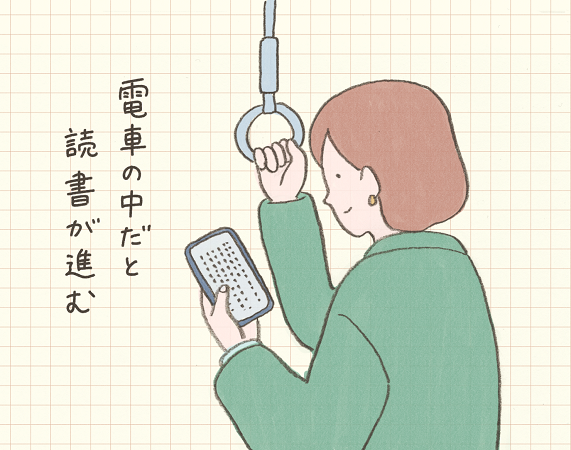
そんなわけで今年読了した本は圧倒的に電子書籍が多いです。
出かけた時に読む本がないと物足りなくなるので、Wi-Fi環境下でKindleや楽天koboで電子書籍をダウンロードしておいて2,3冊は未読の本をストックしておくようにしています。
ご相談者さんはどうですか。どんな時だと読書が捗り、反対にどんな時だと捗らない傾向があるでしょうか?読書したくなりそうな場面があるならそこに本を持ち込んでみてはどうでしょうか。
例えば本を一冊と財布だけを持ってカフェに行ってみませんか?
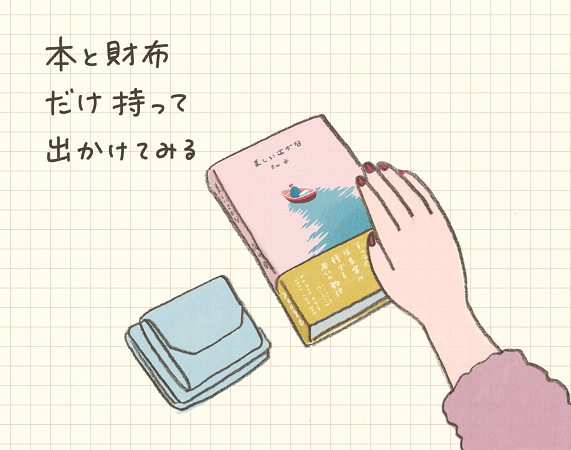
1時間くらいなら、スマホを置いて出かけてもなんとかなるのではないでしょうか。
読書以外の娯楽のない環境に自分を置いてみればページを捲らざるを得ません。
私は座り心地の良いイージーチェアのあるスターバックスに本を持ち込んで読書すると、何より捗っていました。また、温泉に行った際にロッカーに荷物を預けて、本だけ持って休憩スペースに行き読書するのも好きでした。
他には、本棚のあるカフェでそこにある本を読み、続きを読みたくなったら購入したりしていました。続きが気になる状態なので読書が進むんですよね。
もし出かけることのハードルが高ければ、スマホを隣の部屋に置いて家の中で読書せざるを得ない環境を作るのもありです。
1時間も読めば読書気分がのってきて続きが気になるか、あるいは自分に合わない本がわかるのでは。のってきたらその本が楽しみな存在になるでしょう。
読書が楽になる方法
文字を読むのは能動的作業ですが、受動的に読書できるように環境を整えてみれば捗る可能性もあります。私の場合は、音声で読み上げてもらう「聞く読書」も効果的でした。AmazonのAudibleや、audiobookなどのサービスですね。
Audibleで仕事中に小説を聞いて半日で1冊本を読了できました。
仕事中は業務内容的に難しい場合もあるかもしれませんが、例えば洗濯物を畳む時など、家事の中で手を動かすけれど耳が空いている場面は結構あるので、そんな時に聞く読書はおすすめです。
買い直してでも読みたいけれど聞く方が楽だと感じるなら、積読本と同じタイトルを音声コンテンツで買い直すのもアリではないでしょうか。
手放すにせよ読み進めるにせよ、ご相談者さんの心が少しでも軽くなったらと思います。
私も今年は自分の中の情熱を測って、積読の山を崩していきたいと思います。